2021年03月26日10:18
[10]目標金額はいくらがベスト?掲載期間はどれくらいがいい?宣伝ってどんな風にすればいいの?


餃子屋本舗の楠です。ご覧いただきありがとうございます。
前回の記事ではファーストビューについて解説しましたね。
これでページ作りに関するテクニックは全て公開しました。
今回の記事では、私がつまづいたポイントでもある、目標金額の決め方やプロジェクト公開後の宣伝方法について説明します。
クラウドファンディングではページ作りと同じくらい宣伝が大切です。
宣伝しなければ、ページの存在すら知ってもらえず、支援してもらえることは無いからです。

目標金額の決め方は大きく分けて3つあります。

それぞれにメリット/デメリットがあり、金額が増えるにつれて、失敗リスクと資金必要性の説得性(図中の切迫度)が上がります。
また、クラウドファンディングの目標設定では金額そのものよりも、支援者の応援熱を維持できるかという視点が重要だと私は思います。
例えば、大きな目標金額を設定をすると資金必要の説得性が高まりますが、達成率が伸びないと応援熱が冷めて見放されてしまいます。


CAMPFIREの終了間際のプロジェクトを見ると、残り1日を切っても達成率が半分以下のプロジェクトがたくさん見つかります。
https://camp-fire.jp/projects?sort=last_spurt
こうなると、スポーツ試合で大量得点差をつけられているのと同じ状態になるので、ファンですら応援熱が冷めてしまいます。
ですので、現実的に達成不可能な金額を設定するのはオススメしません。
理想的には、プロジェクト終了に向かって少しずつ達成率が伸び、最後のラストスパートで目標達成という流れです。
スポーツ観戦をする際に接戦が盛り上がるのと同じで、注目を集められた方が応援熱を上手く味方につけることができます。

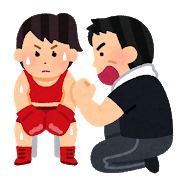
また、私が選択した「実際より少ない目標設定」は、失敗リスクは低いですが、その後の運営が難しいのがデメリットです。
一部の人は達成後も、もっと頑張れと応援してくれますが、「もう達成したからいいだろう」と捉える人も出てくるため、応援熱を十分に生かせないのです。
それを回避するためにネクストゴール(次の目標額を決めること)を設定する手段もあるのですが、私はためらって設定しませんでした。
また、低い目標金額には、以下のようなメリットもあります。
・達成率が伸びやすいのでモチベーションが上がる
・2日で目標達成などと宣伝文句になる
・達成率が高いとリターンが良さそうに感じる


目標設定と同時に検討したいのが掲載期間です。
CAMPFIREの公式ヘルプでは、掲載期間が長いと失敗リスクが高まると指摘されており、65日以下を推奨しています。
私が観察した結果では、支援者が他人ばかりのプロジェクトでは、長い期間を掲載しても最後まで支援は増え続けていました。
しかし、私のプロジェクトのように、主な支援者が知人や関係者の場合は、期間が長すぎると後半はダラけてしまいます。
実際、私のプロジェクトは40日間で、はじめる前は短すぎると思いましたが、今ではこれでも長いと思っています。


CAMPFIREでのカテゴリ別検索順位は、24時間以内(推定)の支援額の伸び高によって決まります。
裏を返せば、支援額が伸びなくなると、下位ページに甘んじることになり、上位に出られなくなってしまいます。
そうなると、知らない人から支援を受けるのは難しくなってしまいます。
その仕組みを逆手にとって、ワザとプロジェクトの掲載期間を10日などと短く設定し、一気に支援額を伸ばして最後まで掲載上位に出続けていたプロジェクトもありました。
また、それと同じように、前半と後半に一気に力を入れて、その期間だけ検索順位を上げる工夫もしているところもありました。
ですから、知人に宣伝する際は小出しにするのではなく、短期間で一気に行った方が検索順位を上げる意味でも効果的です。


通販サイトでも同じことですが、ページを作っただけでは商品は売れません。
宣伝することでページの存在が知られ、はじめて商品の購買が起こります。
それはクラウドファンディングでも同じです。
どれだけ素晴らしいページを作っても、見てもらえなければ支援額は伸びませんので、宣伝することが大切です。
これはCMの影響によるクラウドファンディングの幻想ですが、ページを作れば自動的に誰かが支援してくれると思いがちですが、それはコンセプトがよほど強力な場合だけです。
その証拠に掲載終了間際のページを調べると、支援額がゼロに近いプロジェクトがたくさん見つかります。


実のところ私はページ作りの研究は行っていましたが、宣伝方法についてはそこまで調べていませんでした。
公開ボタンを押してから慌てて取り組んだので、場当たり的な行動になったと反省しています。
ですので、宣伝方法の正解は今も研究中なのですが、ここでは、私が行った方法のうち効果のあったものをご紹介します。
私が今回のクラファンで試したのは以下のとおりです。
・Facebook / Twitterでの告知色々と試してみましたが、本当に効果があったのは以下の3つです。
・Facebook広告
・友人へ直接宣伝
・CAMPFIREのトップページ広告(キービジュアル)
・CAMPFIREのトップページ広告(新着プロジェクト)
・CAMPFIREのニュースレター広告
・Twitterの拡散サービス
・プレスリリース
・店舗でのB0ポスター
・チラシ
・テーブルテント
・友人へ直接宣伝私の今の支援額の8割以上はこの3つでカバーできたと思います。
・Facebook / Twitterでの告知
・Facebook広告
(このうち、いくつかはご厚意により無料掲載していただきました)


私の場合、あらゆる宣伝方法の中で最も効果的だったのは知人に対する「ページシェアのお願い」でした。
プロジェクト公開日、私は知っている連絡先のほとんどに、以下のようなお願いをしました。
「お店がピンチでクラファンに挑戦していて、もし良ければ、このページを●●(学校などのコミュニティ)の知り合いにシェアして欲しいのですが、お願いできますか?あまり連絡先を知らなくて^^;」今思えば、この文をみんなに送ったことが早期達成を手助けしたと思います。
ここでポイントが3つあります。
1.直接支援をお願いしなかったこと
2.ページのシェアをお願いしたこと
3.シェアをお願いする理由を添えたこと


セールスのテクニックで「But you are free」というものがあります。
これは何かセールスしたい時に商品やサービスの概要を説明した後で「けど、選ぶのはあなたの自由ですよ」と添えることで成約率が2倍になるというものです。
このテクニックの本当の使い方は、もっとたくさん話しかけた上で「But you are free」と最後に言うことなので、本家のやり方ではありません。
エッセンスとして取り入れて欲しいのは、最初から支援を強要しないことです。
初期宣伝では、なるべく多くの人にクラウドファンディングをしていることを知らせることが大切です。
ですから、そうした面からも、いきなりハードルの高いお願いをするより、小さなお願いをした方が協力してもらいやすくメリットがありますし、相手も『支援して欲しい』と言われるより遥かに気が楽です。
また、私は行っていませんが、YouTubeなどの生放送を活用してクラファンの説明会を開いているプロジェクトがあり、そうした所は支援額を大きく伸ばしていました。
その際は、「But you are free」は使いやすいので、ぜひチャレンジしてみてください。


また、友人にページのシェアをお願いするときは必ず理由を添えてください。
「影響力の武器」という著名な行動心理学の本で、お願いをする際は「理由を添える」ことで、意図した行動を促せると紹介されています。
実はこのテクニックは、もっともらしい理由でなくても良いことが知られています。
たとえば、コピーの順番待ちをしていて「先にコピーをさせてもらえませんか?コピーをとりたいので」という意味不明な理由でも、94%の人がコピーを先に取らせてもらえたという実験結果があります。
また、私は実際友達が少ないので本当に連絡先を知らないのですが、理由を添えたことで沢山の方からシェアしていただけました。
また、これを応用してフット・イン・ザ・ドアというテクニックも使えるのですが、少し強引なので興味のある方はネットで調べてみてください。

上記のようにお願いをしたことで、私のクラファンは知り合いに一気に広まりました。
また、依頼文の「●●」には中学校・高校・小学校・サークル・スポーツなどあらゆるコミュニティーを指定して宣伝をお願いしました。
そうすることで、複数の人から同じコミュニティーへシェアが起こりますので、ひとりからシェアされるよりも印象に残りやすくなります。
このように宣伝をしたことで、2日で目標金額を達成し、何度か検索上位に表示させることができました。
ただ、何度も言うように、私はメインリターンの餃子をトップ画とタイトルに入れなかったので、そのチャンスを生かすことは出来ませんでした。
ですから、あなたのプロジェクトでは、検索表示でリターンをアピール出来るように必ず工夫してください。


Facebook広告は少額で利用可能ですので、他の広告よりも手軽に行うことができます。
地域・年齢・趣味・家族構成などのFacebookデータを活用し、届けたい人に向けて広告を配信できるので、上手く使えば高い効果が期待できます。
設定方法は他の方が詳しく解説されているので、そちらをご参照ください。
https://webtan.impress.co.jp/e/2019/07/02/32754
ここでは、私が実際に使用した配信先の設定をご紹介します。
<パターン1>近隣
店舗から半径3km以内に住む25歳以上の男女
<パターン2>広域中でも効果を感じたのは近隣向けの<パターン1>です。
・日本に住んでいる30歳以上の男女のうち
・クラウドファンディングに関心があり、その中でも料理/外食に興味がある人 かつ
・最近コールトゥアクションボタン(購入/問い合わせボタン)を押した人
その理由は2つあり、
・お客さんにプロジェクトの存在を知ってもらえた
・シェアした/された知人たちがプロジェクトを思い出すきっかけになったからです。
詳しくは割愛しますが、日本生まれのマーケティング ランチェスター戦略で考えると、ページへの訪問回数が増えると訴求力が2乗になることが分かります。
つまり、1回なら1倍ですが、2回なら4倍、3回なら9倍です。
ですから、ページに何度も足を運んでもらえる方が効果が高くなるのです。
その意味では、SNSを活用すると同じように思い出すきっかけを自然と作れるので効果が上げやすいです。
ただし、宣伝を複数回すると嫌がられてしまうので注意も必要です。
===
今回も長くなってしまいました。
これで、私が紹介するテクニックは以上となります。
ここまで読んでいただき本当にありがとうございました。
舞台裏公開はこれで以上となりますが、私のクラウドファンディングが落ち着いてから、総括として最後の記事を投稿したいと思います。
次回をお楽しみに!
タグ :クラウドファンディング
2021年03月25日11:18
[9]ファーストビューで勝負の7割が決まる!最難関にして最重要なトップページ作りを徹底解説。


餃子屋本舗の楠です。ご覧いただきありがとうございます。
前回の記事では書き上げた文章に装飾を加え、より想いを伝えるためのレイアウトテクニックをご紹介しました。
これで、クラウドファンディングのページ作りに必要なことは、ほぼ全てご紹介できました。
あと残っているのは、最後の難関であり、最も重要なトップページ作り(ファーストビュー)だけです。
「散々ページ作りをガンバってきたのに、まだやらないといけないことがあるのか!」と思うかもしれません。
しかし、この3つの要素にこだわれば、ページを魅力的にするだけでなく、アクセス数を増やすことができるのです。
どんなに素晴らしいプロジェクトページでも見てもらえなければ誰も支援してくれません。
ですから、もう少しだけ踏ん張って、魅力的なファーストビューを一緒に作っていきましょう!
<私のファーストビューの例>

CAMPFIREのプロジェクトページの場合、ファーストビューは3つの要素に分かれています。
[1]タイトル→食べて応援!〜〜の一番上の文章まずは、それぞれの要素がアクセス数にどのように影響を与えるのか説明していきます。
[2]トップ画→私の顔写真が入った画像
[3]リード文→「私は当初〜〜」の太字の文章
じっくり読めばカンタンなので、落ち着いて読んでみてください。

上の画像は実際の検索ページです。
少し見づらいですが、検索結果には、[1]タイトルと[2]トップ画が表示されていますね。
つまり、検索ページを見てクリックしてもらえるかどうかは、タイトルとトップ画の2つで判断されるということです。
ページを見てもらわなければ支援も増えませんから、ここで目に留めてもらうことが非常に大切です。
また、TwitterやFacebookでシェアされる際には以下のように表示されます。
左側がFacebook、右側がTwitterの画面ですが、こうしたSNSのシェア画面にも[1]タイトルと[2]トップ画[3]リード文(一部)が入っていますね。
せっかく友達がページをシェアしてくれても、この3つがイマイチだったらクリックしてもらえる可能性は低くなってしまいます。
支援数を計算式で表すと、「ページの閲覧数×支援につながる確率」となります。
掛け算は両方の数値が上がってこそ数字が大きくなりますから、アクセス数と支援率の両方を高められる[タイトル・トップ画・リード文]は何よりも大切なのです。
当たり前ですが、片方が「0」や「1」では数字は大きくなりませんよね。

タイトルは序盤にたくさんの例を見てきたので、どんなものが良いかの感触は掴めていると思います。
4つの鍵を意識して、あなたの「コンセプトを短く言い表す言葉」+「支援を求める理由」を合わせ、タイトルを付けましょう。

ここには40文字しか入らないので、多くを語ることはできません。
たくさん書いた文章から本当に核になる部分を抽出し、
他と見比べて、あなたのプロジェクトが光っていると感じるまで、何度も何度も検討してタイトルを決めてください。
タイトル選びに迷ったら、過去記事の[2][3]が頼りになるので、再度チェックしてみてください。


1枚目のトップ画像はタイトル以上に重要です。
なぜなら、タイトルには40字の文字情報しか入れることは出来ませんが、トップ画は視覚情報に加え、テキストを重ねることで文字情報も加えることができるからです。
ポイントを2つにまとめました。

ひとつ目のポイントは、写真に文字を重ねることです。
タイトルは40字の制限があるため、どうしても入らずに削らざるをえない言葉があると思いますが、写真の上には制限なく入れられますので入らなかった言葉をここで補足するのです。
実際私の40字以内のプロジェクトタイトルは
食べて応援!「コロナで苦しむ飲食業界の人たち」に支援のバトンをつなぎますというものですが、トップ画像では
食べて応援!「コロナで苦しむ、飲食店、生産者、卸売業者の人たち」に支援のバトンをつなぎます(私も正直ピンチですが、一緒に乗り越えましょう!)じぶんの挑戦の裏側を記録に残して無料公開していきますとして、具体性を高めています。(太字箇所が補足文)
私のプロジェクトは企画が複雑なので、タイトルだけでは具体性に欠ける弱みがありました。
ですから、それをカバーするためにトップ画で企画を簡潔に説明できるように工夫しています。
また、文字を重ねる際に注意して欲しいのは、文字の大きさです。
実際に検索ページで閲覧したときに意図した文字が目立つかどうかを意識してください。
また、文字の大きさは[大・中・小]と使い分け、検索ページ用には[大・中]、閲覧者向けには[小]など区別しましょう。
もちろん、目立たせるために文字を限界まで大きくする手もアリです。


トップ画には、なるべく自分の顔写真とメインリターン画像の両方を入れるようにしてください。
その理由は、支援者の層によって響く写真が以下のように変わるからです。
[1]メインリターンの写真→面識の「ない」支援者に響くCAMPFIREのテレビCMでは『400万人の支援者が待っている』というメッセージを流していますが、ほとんどのプロジェクトでは、主な支援者は、あなたの知人やSNSのフォロワーさんになります。
[2]本人の顔写真→面識の「ある」支援者に響く
ですから、あなたの顔写真をプロジェクトの象徴としてトップ画に出すことが大切です。
また、CAMPFIREで何を支援しようかとサイト回遊されている方は『リターンが何か』を重要視しています。
ですから、顔写真と魅力的なリターン画像の両方を入れるというのが正攻法です。
下記のようなデザインでしたら顔写真とリターン画像をカンタン入れることができますので参考にしてください。



上記は2021/02/19時点でのフード・飲食店での検索結果です。
先程も触れましたが、トップ画やタイトルを考える時には、実際の画面で表示されたときに本当に目立つのかという視点が大切です。
私は自分の考えたタイトルやトップ画像を検索ページに合成して実際にどう見えるかを丹念にチェックしました。
合成が難しい場合は、実際の検索画面を印刷し、手書きで加えたり、写真を横に並べるだけでも十分です。
こうするだけで、パソコンの編集画面を見ているだけでは分からないことに気がつけるので、あなたも少し手間ですが、是非トライしてみてください。


私も盲点だったのですが、トップ画は縦横比「3 : 2」なのですが、SNSのシェア画面は縦横比「1.91 : 1 」です。
ですから、私のプロジェクトは、SNSでシェアするとグレー部分だけが表示されて文字が見切れてしまうのです。
文字を重ねるときは、それを考慮して文字をセンターに寄せた方がシェア画面でコンセプトを伝えられて有利です。
また、トップ画をアップロードすると薄いグレー色の「矢印ボタン・再生マーク」が重なるので、ここに文字が被らないように注意してください。
(矢印&再生ボタンはサムネイルに画像がある場合/動画を埋め込んだ場合に表示されます)


リード文はタイトル・トップ画の次に読まれる確率が高く、ここで惹きつけられるどうかが非常に重要です。
私のオススメは、リードを150字まで書けるタイトルとして捉えコンセプトの概要をコンパクトに伝える方法です。
[6]の記事で桃太郎の話をしたのを覚えていますか?
桃から生まれた桃太郎。おじいさんおばあさんの元、すくすく育つ。この文章は短いけど、物語に必要不可欠要素が詰まっていて、どれが欠けてもストーリーが変わってしまうと言いましたね。
強くたくましく育った桃太郎は鬼退治へ
犬、猿、キジにきび団子を渡して仲間に
見事、鬼を倒して宝物ゲット
これと同じように、あなたのプロジェクトを150文字で表現できるようにトライしてください。
そうすることで、支援者の頭にプロジェクトの概要がインプットされ、本文を読んだときにも理解がスムースになるのです。
また、余裕のある方はSNSのシェア画面で表示される最初の60字で惹き付けることを意識してください。


サムネイルとはトップ写真の下に小さく表示されている写真のことで、クリックすると大きくなって、トップ画像と入れ替わります。
ここも見てもらえる確率が高いので、必ず全て埋めてください。
載せる写真として有効なのは、あなたのコンセプトを最も際立たせ、もっとも見栄えのする写真です。
リターンが食品なら半分は美味しそうなリターン画像にしましょう。
また、あなたの顔が分かるコンセプトに沿った写真も入れた方が良いでしょう。
私は企画が複雑だったので、4コマ漫画風に企画を説明する紙面として使いましたが、これは変則的なのでオススメしません。


CAMPFIREのトップ画には動画を1つまで挿入できます。
動画があると文字と写真だけよりも説得力が遥かに高まりますので、出来れば撮影することをオススメします。
動画はシンプルなもので十分です。
良い例があるので下記リンクのプロジェクト動画を見てみてください。(本文冒頭)

https://camp-fire.jp/projects/view/354429#menu
スマホで撮っただけの動画ですが、見てもらえるとご主人の誠実なメッセージが伝わってきますね。(横で撮った方が良かったですね..!)
色々なクラファン動画を見ましたが、変に凝ったものより、こういうストレートなメッセージの方が心に訴えかけると私は思います。
また、動画は長くなり過ぎない方が良いです。また、原稿は必ず作りましょう。
クラファン動画には、思いが強すぎて何の話だか分からない動画がよくありました。
ですから、あなたのコンセプトが伝わるように、きちんと原稿を作って撮影することを強くオススメします。
内容はリード文をセリフに置き換えて、コンセプトを短く熱く説明するだけで十分です。
3分以内の短い動画で良いので、是非トライしてみてください。

長かったと思いますが、今回の記事でようやくページ作りに関することは終わりました。
何度も言いますが、ファーストビューは今まで説明してきた中でも特に重要です。
難しいとは思いますが、タイトル+リード+トップ画像で言いたいことを「全て伝えるつもり」でがんばっていきましょう!
また、プロジェクトページは出来上がりましたが、クラウドファンディングはこれからが本番です。
どんなに良いプロジェクトページでも知らせなければ無いのと同じですから、スタートしたら宣伝する必要があります。
実のところ私は宣伝方法についてはそこまで調べていなかったので、公開後に慌てて色々とトライしました。
そこでの経験があなたの役に立てば嬉しいです。
次回をお楽しみに!
タグ :クラウドファンディング
2021年03月12日15:04
[8]想いが2倍伝わる!書き上げた文章を見やすく伝わりやすく仕上げるためのレイアウト処方箋



餃子屋本舗の楠です。ご覧いただきありがとうございます。
前回の記事では写真の効果的な魅せ方などについて解説いたしました。
今、私はクラウドファンディングに挑戦中ですが、前回書かれていたような写真のテクニックを使い、現在169%の達成率に届いています。(残り19日)
金額ベースで見ると848,494円と決して多くありませんが、私は特に有名店でもSNSで沢山フォロワーがいる訳ではありません。
条件的に恵まれていた訳ではありませんので、そうした意味からも小さな成功例ですが参考にしやすいと思います。
また、私はたくさんの事例研究をしてからプロジェクトを立ち上げていますが、それでも、やってみないと分からなかったことが多々ありました。
事前に知っておけば「こんなミスはせずに済んだ」「次はもっと上手くやれるのに」と後悔していることも正直あります。
このブログでは、あなたがそんな思いをしなくても良いように、私が失敗したことについても説明していきます。

今回お伝えするテーマはページを作り上げる際のレイアウト方法についてです。
なぜ、そんなことをするのかと言うと、あなたの伝えたいことを短時間で支援者に理解してもらうためです。
悲しい現実ですが、あなたがどれだけ一生懸命に書いた文章でも、ほとんどの人は最後までじっくりと読んでくれません。
読んでいる最中にも、LINEでメッセージが届き、プッシュ通知でニュースが次々に飛び込み、関心を奪い合う時代ですから、短時間で読める工夫を施さなければ、途中でページを閉じられかねません。


短い時間で支援者に想いを届けるために有効なのは「小見出し」を積極的に使うことです。
小見出しとは、本の目次のようなもので、このページで言うところの「テクニック1〜〜」と書いてある部分のことです。
以前、私が提供した文章作成のテンプレートには「お題」がありましたね。
その名前を変えるだけで小見出しの出来上がります。
<文章テンプレート>たとえば、私の例でいえば、<▶商売のエピソード>を「ジャズミュージシャンから実家の餃子店の跡継ぎに」としています。
▶ごあいさつ(そのままでも可)
▶あなたの商売について
▶あなたの商売のエピソード(苦労して乗り越えてきた話など)
▶このプロジェクトを立ち上げたきっかけ(コロナの影響など)
▶このプロジェクトで実現したいこと
▶情熱を込めてリターンの紹介
▶資金の使い道(そのままでも可)
▶最後のメッセージ(そのままでも可)
他にも、文章の長いところは300文字くらいを目安に分割して、そこにも小見出しを入れてください。
小見出しは本文よりも遥かに読まれやすいので、長い文章であれば分割してタイトルをつけた方が有利です。
そうすると、人によっても差があると思いますが、全部で10個ほどの小見出しができますね。
どんなタイトルをつけるかについては、次の太字の説明を参考にしてください。
[参考:文字数カウントサイト] http://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htm

原稿で特に強調したい箇所・コンセプトの種を言い表す文節は太字で強調しましょう。
「6」でご説明した童話 桃太郎の話を覚えていますか。
ここでは桃太郎のストーリーを60文字で以下のようにまとめていましたね。
桃から生まれた桃太郎。おじいさんおばあさんの元、すくすく育つ。第六回目の記事では、この要素をひとつでも変えると、ストーリーが変わってしまうということをご説明しましたね。
強くたくましく育った桃太郎は鬼退治へ
犬、猿、キジにきび団子を渡して仲間に
見事、鬼を倒して宝物ゲット
こうした、あなたのストーリーに外してはいけない箇所は必ず太字にしてください。
そして、最低限、この太字と小見出しさえ読んでもらえれば、話の4割は理解してもらえるように工夫しましょう。
注意したいのは、太字はつけ過ぎると目立ちにくくなりますから、最小限にとどめることです。
本文の20%くらいを目安に試してみてください。
また、参考までに私のプロジェクトでどこを太字にしたのかチェックしてみてください。
<私のプロジェクトページの例>
私は元々はジャズベーシストを志していたのですが、
リーマンショックで廃業の危機に立たされた両親の餃子店を手伝いはじめたことがきっかけで後を継ぎました。
そのときは潰れる寸前まで追い込まれましたが、家族で力を合わせて乗り越え、二年前には店舗を二倍に増床し、フルリニューアルオープンも果たしました。
しかし、今回の新型コロナウイルスにより、
大阪では二度目の緊急事態宣言が発令され、予約のキャンセルが相次ぎ、またもや大打撃を受けました。
正直なところ、廃業しようかと真剣に悩むほど厳しい状況ですが、
大変な思いをしているのは私だけではありません。他の飲食業界の方も同じように苦しんでいます。
ここで太字にしてあるところが、私にとってのコンセプト種(桃太郎の核)です。
ご覧いただくとパッと見てスグに赤色の小見出しが目に入り、次に太字のワードが目に飛び込んでくるのがお分かりいただけるかと思います。
こんな風に、小見出しと太字を意識して使ってください。それだけで想いは断然と伝わりやすくなります。

写真の下にくっついている文章は「キャプション」と呼ばれ、
本文より4倍も多く読まれることが研究によって明らかにされています。
それほど注目される箇所なのですから、キャプションはなるべくつけるようにしましょう。
ただ、ひとつ注意点があります。
先程、㊤でご紹介した私のプロジェクトページの例(太字項目)を見ると、キャプションをつけている所とつけていない所がありますね。
これには理由があるのですが、キャプションを入れ過ぎると本文が読みづらくなってしまうのです。
ですから、一旦ハメ込んでみて、読みづらいと感じたら取りましょう。
キャプションの内容は、太字の時と同じようにコンセプトの種(桃太郎の核)やそれを補強するようなワードにしてください。
ちなみに、CAMPFIREにはキャプションをつける機能が最初から備わっています。(画像を入れてマウスオーバーすると項目が出てきます)

以上が、想いを届けるために必要なテクニックです。
今挙げた「小見出し・太字・キャプション+写真」だけで言いたいことが6割は伝わるように意識してください。
原稿を書くときは、どうしても本文ばかりに集中してしまいますが、この段階では読む人の気持ちになって、ページをザッと見たときに伝わるのかという視点でレイアウトを作っていきましょう。
このステップを経るだけでも、あなたのページ作りはワンランクもツーランクも引き上げられます。

あなたも経験があると思いますが、
文字がビッシリと書かれたサイトを見ると「ウッ」となって読む気が起こらないことってありませんか?
<例えば、こんな感じです>
実は、パソコンで何気なく書いた文章を、スマホでチェックすると文字だらけになることってよくあるのです。
これでも読めないこともないですが、読みにくいので離脱率が高まってしまいます。
それを回避するのが改行です。
その例として良いのは、今あなたが読んでいるこのページです。
基本的には句点「。」で一行空け、長い文になるときは読点「、」でも一行空けています。
パソコンで見ると少し違和感があるかもしれませんが、ほとんどの人はスマホで閲覧しますから、モバイルでの読みやすさを優先させてください。
また、プロジェクトページの編集は大抵パソコンで行うため、よっぽど意識しないと、気づかないうちに「文字だらけの罠」に掛かってしまうので注意してください。
それを回避するための、スマホブラウザチェックの小技があるのでご紹介します。
ChromeやSafariなどのブラウザには実は開発者向けにPC上でスマホ画面を確認できるツールがついています。
私はChromeをメインに使っているのですが「F12」を押すとスマホブラウザで確認できる機能が立ち上がります。(ファンクションキーやOSによっても変わります)
<PCでスマホブラウザを見た時の画面>

こんな感じで見えますので、いちいちスマホで確認しなくても作業が捗るので便利です。
また、○で囲んだところから画面サイズを変更できますが、最新機種にしないように注意してください。
現在のスマホの画面サイズの平均値は5.59インチだそうですが、普及とはタイムラグがあるので、少し控えて考えた方が無難です。
私はだいたい4.7インチ(iphone SE2)くらいの見え方で調整しました。
また、ある程度仕上がったら自分のスマホでもプレビュー画面を見てください。
タッチ操作とマウス操作、画面と顔の距離が違うと受ける感覚も変わるので、最終的なチェックは私もスマホで行っています。
PCでスマホブラウザを見る詳しい方法はコチラから
↓
https://www.buildinsider.net/web/chromedevtools/01


上の画像はスマホで見たときの私のプロジェクトを繋ぎ合わせたものです。
ここで見てもらいたいのは文字と写真の間隔です。
私が意識したのは、スマホ画面で見た時に「全て文字だけのページ」をなるべく作らないということです。
文字の間にバランスよく写真を挟むことで適度なスピードで読み手がスクロールしていけるように考えています。
この手法は以前紹介したイベリコ豚の生ハムプロジェクトで使われています。
文字がぎゅっと詰まっていると、スマホで同じ箇所をずっと眺めることになり読み手が退屈してしまいます。
かといって写真だらけだとスクロールが早すぎて文字が流れてしまいます。
そのバランスに気をつけて改行を組み合わせましょう。
また、私のプロジェクトページでは本当に伝えたいことは、写真を無くして文字だけにしています。
こうしてメリハリをつけることで、文字だけのページでも読んでもらえるようになるのです。
===
以上が、書き上げた文章を伝えるためのテクニックです。
手を入れていくほど自分のページが見やすくなるのを実感できるはずです。
少し大変ですが、ガンバっていきましょう。
今回の記事は以上です。お疲れさまでした!
あと、残すところはトップページですね。
がんばっていきましょう!
タグ :クラウドファンディング
2021年03月09日11:05
[7]感情移入を引き起こす写真作成のテクニック/イマイチ写真をうまく使う方法を紹介。


餃子屋本舗の楠です。ご覧いただきありがとうございます。
前回の記事では文章の書き方について詳しくご説明させていただきました。
「童話 桃太郎」を例に出して伝わりやすい文章に必要な要素をまとめてお伝えしましたね。
今、あなたは文章作成に取り組んでいるところでしょうか?
ひょっとしたら、とても大変だと投げ出したくなっているかもしれませんね。
大切なのは一歩ずつ着実に進むことです。
煮詰まったら無理に進む必要はありませんので、少しずつ休みながら取り組んでいきましょう。

今回のテーマは写真です。
以前の記事でも成功プロジェクトには写真が多いということをお伝えしましたね。
それをもう少し詳しく分析すると、成功/失敗プロジェクトには写真点数に以下のような傾向があることが見つかりました。
・成功プロジェクト→25枚以上また、その写真の中身を分析してみると、
・失敗プロジェクト→10枚以下
・リターンの商品写真が10点以上と半数という結果になっています。
・コンセプトをイメージ化する写真が10点以上
写真には文字には持たない、視覚に訴えかける力があるので、
文字と組み合わせることで、支援者にあなたの気持ちをダイレクトに届けることができます。
その威力を感じていただくために、今から参考プロジェクトをご紹介して、どんな写真を選べば良いのかご説明します。

創業40年!秘伝のたれで焼いた国産鰻の蒲焼きを食べて養殖場を救ってほしい

https://camp-fire.jp/projects/view/357687#menu
リターンが食品の場合はとにかく美味しそうな写真をたくさん掲載しましょう。
ここで最も参考になる事例はこちらです。
一度、ご紹介した鰻屋さんのプロジェクトですが、ぜひ実際のページを覗いてみてください。
写真を見ていただくと、そのほとんどの写真が鰻に関係するものばかりです。
その数はなんと13枚です。
注目していただきたいのは鰻重の写真だけでなく、鰻をさばいた写真、蒲焼きにしている写真、蒸している写真など調理工程が随所に散りばめられているところです。
このテクニックは是非真似していただきたいのですが、こうして調理中の写真を挟むことで、美味しさの期待値を高めることができます。
高級料理店に行って板前の調理風景を見ていると期待が膨らんできますね。それと同じ理屈です。
このプロジェクトでは人の顔写真・店舗の写真が一切写っていないのですが、それでも成功しているのは、
コンセプトの良さに加えて、この美味しそうな写真の複数掲載が、支援者の「食べたい」という気持ちを後押ししたしたからです。

1894年築の古蔵で移住夫婦が造る「メイドイン尾道」のクラフトビール
 https://camp-fire.jp/projects/view/344244#menu
https://camp-fire.jp/projects/view/344244#menu コンセプトを際立たせるイメージ写真というのは、文章内で語るエピソードをリアルに感じさせてくれる写真です。
文字だけで想いをスケッチするよりも写真を載せた方があなたが伝えたい情景がアリアリと伝わります。
その模範例としては再度の登場となりますが、こちらの夫婦のプロジェクトが参考になります。
このプロジェクトは商品そのものより、夫婦二人三脚で取り組んできた軌跡がコンセプトの種となっていて、
文章と共に、その時々に撮影された夫婦の写真が掲載されています。
ビール工場の仲間たちとの集合写真、何気ない日常の写真、古屋を改装している写真、夫婦のツーショット、仕込み風景などを見ていると、
文字を読まず、写真だけを追っていてもストーリーがスッと入ってきますね。
ここが写真選びで非常に重要なポイントです。
ページを読んでいくと、写真のお陰で文章の内容がよりリアルに感じられ、共感の気持ちが沸いてくることに注目してください。
あなたのページでも、こういった写真選びを心がけましょう。

地球にも胃腸にも優しい「発酵ヴィーガン餃子」を全国の人に届けたい
 https://camp-fire.jp/projects/view/359655#menu
https://camp-fire.jp/projects/view/359655#menu まずはリンク先をご覧ください。
「直感を信じて〜」という見出しに対して、大きな写真1枚と、その下にコラージュ写真が配置されていますね。
このようなコラージュ写真は1枚の写真を並べるよりも、さらにコンセプトの視覚化が促されます。
仮に大きな写真を同じ位たくさん入れると、写真だらけで本文が読みづらくなってしまいます。
ですから、こういうコラージュ写真にすることで、
ストーリーの視覚化を強く促し、本文も読みやすくできるのです。
また、コラージュ写真の最大のメリットとして、ピンボケ写真や、イマイチな写真でも使えるという点が挙げられます。
過去の写真から見栄えのする写真ばかりを探すのは非常に難しいですが、
コラージュですと、微妙な写真でも強力な効果が得られるのでオススメです。


写真集めで注意したいことがあります。
誰でも経験があると思いますが、アルバム整理をすると、つい昔の思い出に浸ってしまい、意識しないと時間ばかりが経過してしまいます。
それではいくら時間があっても足りませんので、写真集めでは強い意思を持って素早く終えましょう。
そのためにオススメなのはABCランク分けです。
Aランク...メイン写真に使えるほど良い写真アルバムをひっくり返してA/Bランクに入るものだけをピックアップしてフォルダ分けしていくのです。
Bランク...少しボケていたりするけど使えそうな写真(コラージュ用や第二候補として)
Cランク...今回のクラファンには関係のない写真
関係のない写真は潔くCランクとしてスパっと振り分けましょう。
また、この段階では1枚1枚の写真を丹念にチェックしなくて大丈夫です。
ページ作りの段階で再度チェックしますのでスピード優先でザックリ進めていきましょう。
また、Bランク写真には、半目・赤目・ピンぼけ・ブレた写真も含めてください。


写真はデジタルデータでなくても、現像された写真もスマホアプリで読み込んで使えます。
綺麗さには欠けますが、歴史のある写真にはそれがちょうど良かったりもします。
私が普段から使っている無料アプリのリンクを貼っておきますので参考にしてください。
https://apple.co/3br9rUZ
(初期設定ではカラーモードが「白黒」になっているので「カラー写真」に変更してください)
直感的に使えるアプリですが、念の為使い方をまとめたサイトを貼っておきます。
https://appleshinja.com/scannerpro-usage


食品のリターン写真は出来ればプロが撮影した写真を使いましょう。
コンセプトの写真については普段撮っているようなスマホ撮影でも十分ですが、それでは美味しさを伝えるのは困難です。
高画質なスマホを持っている場合は下記サイトのような方法で撮影するのも良いと思いますが、どうしても時間がかかります。
https://hue-hue.com/media/smartphone01/
ですから、予算が許すのであれば、プロのカメラマンに撮影してもらった方が時間短縮も出来てオススメです。
プロもピンきりですが、複数枚の撮影で1万円くらいとリーズナブルな料金設定をされている方もいらっしゃいます。
探す方法は「地域名 カメラマン」で検索すればヒットします。
カメラマンごとにサンプル写真が出ているので、それを見て良さそうな人に依頼しましょう。
また、依頼する際は、こんな写真を撮ってほしいと先にカメラマンにイメージを共有しておきましょう。
Google画像検索などで撮影して欲しいイメージを保存し、プロジェクトページへ当て嵌め、それをカメラマンに見せて、何を何点撮影して欲しいと依頼の際に伝えておくのです。
ちょうど、美容室に写真を持っていって「こんな髪型にしてください」というのと同じですね。
その方がカメラマンも事前準備がしやすいですし、撮影時間が短時間で済むので料金も節約できます。


写真は全て自前で用意する他、レンタルという手段もあります。
ネットで「レンポジ」と検索すると、プロが撮影した写真をレンタルできる素材屋(有料)さんが出てきます。
あなたの商品がオリジナリティが高い場合は残念ながら使えないのですが、
たとえば、霜降り牛肉の断面のような汎用性のある写真であればレンポジは相性が良いです。
カメラマンに依頼するのと違う点は、雑誌の表紙を飾れるようなクオリティの高い写真を気軽に使える点です。
さきほど紹介した数時間1万円のカメラマンに見惚れるような写真を期待してはいけません。
飲食店に大衆店や高級店があるようにカメラマンの腕も値段によってピンきりです。
ここでは具体的に言えないのですが、定額制プラン(月間)を上手く使えば費用も抑えられますので、検討してみてください。
また、当たり前ですが、ネット画像を許可なく勝手に使うのは違法ですから注意してください。

今から私がご紹介したいのは同じ発起人が立ち上げた2つのプロジェクトです。
この発起人は7回に渡ってクラウドファンディングに挑戦されており、
1.000万円に超えの支援金を複数回獲得されています。
しかしながら、この方も最初から上手くできた訳ではありませんでした。
はじめてのプロジェクトでは支援額は50万ほどで目標未達となっています。
この同じ人物が立ち上げた2つのプロジェクトを見比べることで、たくさんの気づきが得られると思いますので、
特に写真の内容・語っているエピソードについてチェックしてみてください。
<はじめてのプロジェクト:廃棄肉に新たな価値を!イベリコ豚のホルモンを和食の力で広めたい!>
 https://camp-fire.jp/projects/view/150698
https://camp-fire.jp/projects/view/150698 <7回目のプロジェクト:黒毛和牛とイベリコ黒豚のお肉を破棄から救って食べて消費してほしい>
 https://camp-fire.jp/projects/view/357633#menu
https://camp-fire.jp/projects/view/357633#menu いかがでしたでしょうか。
写真もそうですが、コンセプトの作り方も全然違っていたことに気づいたのではないでしょうか。
はじめてのプロジェクトではデザインも凝っていて可愛らしいものでしたが、
クラウドファンディングの支援者の心をつかむものではありませんでした。
しかし、この方は諦めずに何度も挑戦することで、1.000万円以上の支援金を集めるプロジェクトを立ち上げられるようになったのです。
こんなにも参考になる教科書があるのですから、
しっかり学び取って、自分の企画に生かしていきましょう!
===
次回の記事では、あなたのページをより伝えるためのテクニックをご紹介します。
お楽しみに!
2021年03月05日08:03
[6]キモチを伝えるクラファン文章術。童話「桃太郎」から学ぶ文章作成の必須条件を解説。


餃子屋本舗の楠です。ご覧いただきありがとうございます。
前回の記事ではリターンについて詳しくご説明させていただきました。
商品券をリターンにする際の問題点、利益額だけで価格を決めてはいけないこと、クラファンには収支以上に宣伝効果も大切だということについてお話させていただきました。
今、あなたには、コンセプトの種(4.参照)とリターンの構想が頭にぼんやりとあるはずです。
今回はそれを膨らませて、実際に書きながらプロジェクトを作り上げていきましょう。
今までで一番長い章になりましたが、じっくり取り組んでいきましょう^_^


今からテンプレートに沿って原稿を書いていただくのですが、文章に起こす前に意識していただきたいことがあります。
少し抽象的な話なので、誰もが知る童話「桃太郎」を例に挙げて説明してみたいと思います。
桃太郎のストーリーは簡単に言うとこんな感じですね。
桃から生まれた桃太郎。おじいさんおばあさんの元、すくすく育つ。今、説明に使ったのは80文字ですが、ここには「桃太郎」の物語の核が詰まっています。
強くたくましく育った桃太郎は鬼退治へ
犬、猿、キジにきび団子を渡して仲間に
見事、鬼を倒して宝物ゲット
ここが少しでも変わると「桃太郎」とはかけ離れた童話になってしまいます。
たとえば、桃太郎から「桃から産まれた事実」を無くしたら「ただの太郎」ですよね。
また、鬼が登場しなくなって、ただの宝探しになったら、もはや別の物語になりますね。
このように、この80文字に含まれている要素は桃太郎の物語を支えるために必要不可欠な部分だということがお分かりいただけるかと思います。
逆に、桃太郎に新しい要素を付け加えてみましょう。
たとえば、桃太郎のおじいさんとおばあさんには実は過去に生き別れた伴侶がいて実は二人は再婚組だったとします。
物語の中にそんな複雑な事情が加わったらどうでしょう。
その裏話は面白いかもしれませんが、語ることで桃太郎のストーリー性が壊れてしまいますよね。
鬼退治するのが物語の主軸なのに、おじいさんとおばあさんの過去の話は必要ないからです。


 これをあなたが書く文章に置き換えて考えてみましょう。
これをあなたが書く文章に置き換えて考えてみましょう。『事実は小説より奇なり』という言葉があるように、私たちが経験する日常は桃太郎のように分かりやすくはありませんよね。
あなたが今から文章に起こす内容はコロナ禍における自分の境遇ですから尚更です。
それをありのまま書くと、複雑すぎて伝わりづらくなってしまいます。
ですから、あなたの事情の一部分にスポットライトを当てて、シンプルなストーリーにする必要があります。
あなたにとって大切なエピソードだったとしても、もしかすると、それは桃太郎における「おじいさんとおばあさんの境遇」の話と同じかもしれません。
そうであれば、今回のクラファンではそれは語らずに、あなたの中だけにソっとしまっておいてください。
こうして余計な要素を削ぎ落とすことで、相手にストレートに伝わる文章が仕上がるのです。
また、文章を書きはじめる前には、登場人物を整理しておきましょう。
桃太郎における、きじ・いぬ・さる・鬼・おじいさん・おばあさんの役割を果たす要素があなたの物語にもあるはずです。
一生懸命書いても、鬼が抜けては物語として成立しなくなるのです。

成功しているプロジェクトを見ると、文字数は3.000文字〜4.000文字くらいです。
理想は長すぎず、短すぎずです。
長すぎと途中で読むのがイヤになってしまいますし、短すぎると「やる気がない」と思われてしまいます。
私は実際に書くときには10.000文字くらい書いて、それをギュっと凝縮させて4000文字くらいに納めました。

文章に起こす、私のオススメ方法があります。
ある程度の登場人物(要素)を整理してやストーリーの方向性をメモにまとめたら、
その後は文章が崩れても気にせず、言いたいことを好きに書いてから修正する方法です。
その理由は、文章作成は書くよりも修正時間の方が長く使うからです。
序盤のうちに細かな文字表現に気を配ったとしても、文章を修正するうちに文節が繋がらなくなって、せっかく時間をかけた箇所も修正するハメになります。
ですから、下書きの時は崩れていても途中で文が飛んでも書くことだけに集中します。
そして、ある程度仕上がったら再読し、不要な箇所を削り、違和感のあるところを修正し、文章を作り上げていきます。
こうして、「削る&言い換える」を繰り返すうちに伝わりやすいメッセージが生まれていきます。


書いていると、どうしても表現したい言葉(単語)が出てこない時があります。
そんな時は類語辞典を活用しましょう。
近い言葉を検索すると、目当ての単語が出てきます。
https://thesaurus.weblio.jp/
検索すると適切だけど難しい言葉がたくさん見つかるのですが、それは避けて、誰でも理解できるカンタンな言葉を選んでください。
クラファンは文章レベルを競う場ではありませんから、誰が見ても理解できることが最優先なのです。
また、文章の言い回しも「伝わる」が大切なので、ひとつの文節を短く切り、読みやすさを意識してください。
特にPCでは数行の文でもスマホでは5〜6行にもなって読みづらくなることがよくあります。
そのあたりのテクニックは、また別の記事で詳しくご説明していきたいと思います。
それでは、テンプレートに沿って早速書いて行きましょう!

※コピーして使ってください
▶ごあいさつ
▶あなたの商売について
▶あなたの商売のエピソード(苦労して乗り越えてきた話など)
▶このプロジェクトを立ち上げたきっかけ(コロナの影響など)
▶このプロジェクトで実現したいこと
▶情熱を込めてリターンの紹介
▶資金の使い道
▶最後のメッセージ

はじめまして、○○県の○○市で「 」営む、フルネームと申します。
からはじめて、ここでは支援者に向けて簡単に自己紹介をしましょう。
書くときに迷ったら私のプロジェクトを参考にしてください。
<参考>https://camp-fire.jp/projects/view/370372

自分がどんな商売をしているのかを支援者に説明しましょう。
コンセプト作りのワーク「Q1」から選んだコンセプトの種を内容を膨らませて、
自分が商売をはじめようと思ったキッカケなどのエピソードを交えて、
相手の頭の中に物語が広がるように書いていきます。
いまは文章が変になっても気にせず手を進めていきましょう。
ひと段落してから見返して修正していけば大丈夫です。

コンセプト作りのワーク「Q2」から選んだコンセプトの種の内容を膨らませて、
あなたがこれまで奮闘してきたエピソードを書いていきましょう。
相手にもあなたの気持ちがリアルに伝わるように、うまいこと書く必要はありませんが、伝えることを意識してください。
成功しているクラウドファンディングにはとびきりの文才が無くても「伝えたい!」という気持ちが滲み出ているものは成功しています。
あなたはこれまで色んな思いを抱えて商売をしてきたはずです。
その思いを、その歴史をここでぶつけましょう。
<伝えたい気持ちがにじみ出た参考事例>
https://camp-fire.jp/projects/view/365436?list=food_popular_page2

コンセプト作りのワーク「Q3&Q4」から選んだコンセプトの種の内容を膨らませて、
あなたの商売に及ぼした「コロナの影響」を一般の人に向けて分かりやすく書いていきます。
ここでは曖昧な言葉でなく「幕を閉じてしまう」「このままでは存続が難しい状況」などリアリティのあるシンプルで具体的な言葉を選びます。(嘘は絶対駄目ですよ!)
こんなにも頑張ってきた人が、希望に溢れていた人がコロナをきっかけに廃業に追い込まれるのは駄目だと支援者に思ってもらってください。
自分の置かれている状況を遠慮して書くと失敗につながるのは、これまで見てきたとおりです。
不安な気持ち・恥ずかしい気持ちがあるのは私も分かりますが、結果があなたを癒やしてくれるはずです。
がんばって乗り越えていきましょう!

コンセプト作りのワーク「Q5&Q6」から選んだコンセプトの種の内容を膨らませて、
このプロジェクトを通じて、あなたがどんなことを実現したいのかを書いていきます。
クラウドファウンディングでは夢や希望を後押ししたいという支援者が多くいらっしゃいます。
残念ながら暗いままでは誰も手を差し伸べてくれません。
大変な状況でも希望に向かって、強く突き進もうとしている人を、みんなが応援しようとしてくれます。
あなたは他の人に支援していただいて、コロナを乗り越えてどんな風になりたいのでしょうか?
支援者は、あなたが何をしようとしているのかを真剣に見ています。
それに共感できるかどうかが支援の分かれ目です。

あなたの自慢の商品を思い切りアピールしてください。
何度も書いていますが、支援者にとってリターンの魅力度はとても大切なので、特にここは気合いを入れて書きましょう。
あなたの商品を美味しそうと思ってもらうコツは、以下の2点です。
1.おいしそうに感じる「擬音語や表現」を入れる
2.おいしそうを「裏付ける理由」を入れる
簡単にご説明します。
まずは、あなたの商品の美味しそうを言い表すワード(擬音語/表現方法)を探してください。
下記サイトにたくさんの例が載っているので参考にしてください。
また、自分に関連するものだけを手っ取り早く見たい方は、似た商材を扱う通販サイトを参考にしましょう。
https://bit.ly/2MIIVgm
上記サイトを見ると、「なめらか、旨味のある、濃厚な、ほんのりと甘い」などのおいしさを連想させる言葉がたくさん見つかりますね。
そこから、自分の商品に合うものだけを集めてください。
そのあと、その「擬音語/表現」に対する説得力のある理由を添えてください。
たとえば、モチモチ食感のパンがあるとしましょう。
世の中にモチモチのパンはいくらでもありますから、理由を添えることで差や説得力を出す必要があります。
たとえば、モチモチでしたら湯種製法だから/製菓用の米粉/北海道産の中力粉を使っているからなどの理由が見つかると思います。
そうした情報も一緒に入れるのです。
すると、
私共が作り上げる食パンは、北海道産の中力粉「北の誉(ほまれ)」を用いて湯種製法で丹念に仕上げているため、今までにないモチモチの新食感を実現しました。トーストにして頂ければ香ばしい小麦の風味と共に粘りのあるモチっとした食感が味わえます。などと言えるため、擬音語だけが並んでいるだけよりも説得力が遥かに増すのです。
ですから、リターンの紹介では「美味しさの表現+製法へのこだわり」をセットで説明することを意識しましょう。
また、「製法へのこだわり」に使える素材ををヒントとして挙げておきます。
●素材の産地(北海道の希少な国産小麦を...など)
●調味料や素材の組み合わせ
(群馬県産の小麦にフランス産のエシレバターを組み合わせたラスクにゲランドの塩をひとつまみ)
●仕込み時間をアピール(13時間煮詰めた/丸2日煮込んだ)
●調理方法(焼く・煮る・蒸す・茹でるや下処理なども含む)
●調理人の経験(〜〜ホテルで総料理長を務めた・この道ひと筋三十年の職人が...)
などです。
私はメニューブック作りが専門なので本当はここが一番ノウハウが多いのですが、書くと紙面を取り過ぎてしまいますので割愛いたします^^;
もし迷った場合は自分と似た商材を扱う通販サイトを覗いてみてください。
サイトの丸パクリはいけませんが、参考にして変化を加え掲載するのはOKです。

支援された金額で何かを購入する予定などがあれば、詳細に記入しましょう。
特にリターンの金額を通常価格より上乗せしている場合などは、
ここにしっかりと情報がなければ不自然になってしまうので注意してください。
簡単に書いていらっしゃるところでは、「運転資金・リターンの準備金」程度で済ましている方も多いです。
<例>
https://camp-fire.jp/projects/view/347075?list=projects_popular_page8

ここでは支援者に最後のお願いをしてください。
うまいこと言う必要は無いのですが、善意で支援をしてくださる方に誠実に支援のお願いをしましょう。
よくあるフレーズは「私たちに皆様のお力をお貸しください」と結ぶパターンです。
===
以上が、私が提供するテンプレートです。
また、CAMPFIREが提供しているテンプレートもあるのですが、そこには実施スケジュールというものがあります。
この資料をご覧いただいている方は自分の商品をリターンにされる方が多いと思うので不要かと思います。
とても長くなりましたが、ここまで読んでいただいてありがとうございました。
次回は、書き上げた文章を、より支援者に伝えるための写真作成テクニックについてご紹介します。
また、文章の太字の付け方や、小見出しの作り方については、また後日解説しますので、
今は気にする必要はありません。
それでは、また次回にお会いしましょう!







